先生の勉強部屋
公開保育
平成25年11月26日(火)に公開保育を実施しました。




PDFを閲覧するにはAdobe Readerが必要です。
ダウンロードしてご覧ください。
職員会議の様子

毎日 3:00から会議を行っています。
その日の欠席状況や落し物の確認、問題等が起きた場合の解決策、行事の打ち合わせで全員の共通理解を深めます。
保育内容の研究
- ■研究保育として、お互いに保育を見学し合い、その後反省会をして次の保育に生かしています。
- ■毎日の保育についての週案作成(自己評価と園長チェック)
- ■参観等の指導案作成
園内研修を実施

キンダーカウンセリングの先生との懇談で、コミュニケーション力を磨きます。
そして、先生のメンタルケアにも留意しています。

コミュニケーション力向上の為の研修
*講師 松下直子 先生
社会保険労務士
人材育成コーディネーター

教職員への研修として絵画指導研修を行っています。

体育指導研修
*講師 田村成 先生
運動あそびアドバイザー

防犯指導研修


救命指導研修
園外研修に参加
- ■大阪府 新規採用教員研修
- ■ 〃 就学前人権教育研修
- ■ 〃 保育技術専門研修
- ■ 〃 園長等専門研修
- ■ 〃 幼稚園連盟主催研修
- ■堺市教育委員会主催研修
- ■堺市私立幼稚園連合会主催研修
- ■夏期 保育技術研修
- ■公開保育見学
- ■幼児教育実践研究報告会
研究発表
平成21年3月7日(土)に行われた 第3回 幼児教育実践研究報告での発表をご紹介します。


人と共存していく為に重要なことは、上記にあります他者理解、人に対する思いやりです。
「排他行動」と呼ばれる他者を排除する行動、自己中心的な行動から、「愛他行動」他者を愛する、思いやることへの移行です。
この「愛他行動」は、年上から年下へ圧倒的に多く表れることから、本園では異年齢の活動を意図的に確保していく中で、他者に対する思いやりを育て、人と共存する力の基礎作りを実践しています。
研究経過


研究経過は、①~⑤に示しています。
縦割保育の中で、年長児は年下の友だちに優しく接していますし、年長児の様子から模倣して学べることも多いです。
登降園の送り迎えも毎日行っているので、異年齢の関係が深まり、年少児は年長のお兄ちゃん,お姉ちゃんを頼りにしています。
お店屋さんごっこの時も年長児と年少児が一緒に買い物に行く様にしていますが、年少児に合わせて腰を曲げたり、目線を下げて話している様子はほほえましいものです。
保育者が、「小さい組の子に目線を合わせてあげてね」と言うことはありません。
日々の関わりの中から学んだ思いやりがはっきり表れています。(写真左側)
①~④の設定した活動の体験が、原動力となって2学期の運動会以降、保育者の働きかけがなくても自主的に年下の友だちと関われる様になってきます。
自由な外遊びの時にも その様子が表れてきて、砂場で楽しそうにしゃべりながら、異年齢の子どもが遊んでいるのが分かります。(写真右側)
少子化で兄弟が少なくなっていることに加え、公園や空き地で子どもだけで遊ぶことが難しい現状では、異年齢の関わりを広げられる全園児の外遊びを大切にしていきたいです。
保育者はその時間をできる限り取れる様に、雨上がりでも遊具を拭き、水溜りの水取りをして外遊びに出す様、努めています。
多くの人数で遊ぶと多少のケガがあったり、子ども同士のぶつかり合いもありますが、集団生活での実体験こそ、子どもの成長につながるのだと思います。
全園児の外遊びの様子

異年齢の関係を小学校へも繋げる
園での異年齢の関わりに加えて、11月に1回ではありますが、堺市立向丘小学校との交流を行っています。
いつもは年下の子のお世話をしている年長児も、その日は逆に1年生のお兄ちゃん,お姉ちゃんに色々と優しく接してもらって嬉しかった様ですし、小学校への期待も膨らんでいます。
これらの機会を通して、「愛他行動」がどんどん広がり、人と人が仲良く共存する社会になれば、すばらしいことです。


保護者への働きかけについて
平成21年4月から幼稚園教育要領が改定され、家庭との連携の強化が示されています。
本園での取り組みは、改定された教育要領に揚げられている4つの例示に当てはまるものです。
情報提供 参考資料
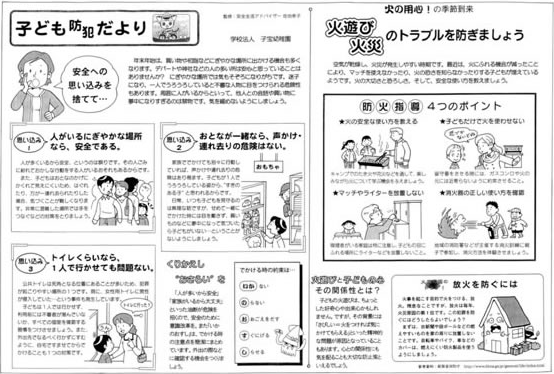
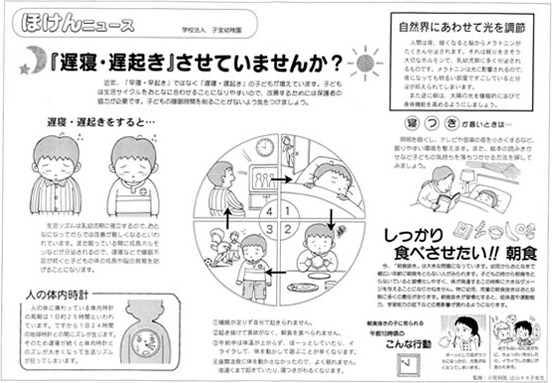
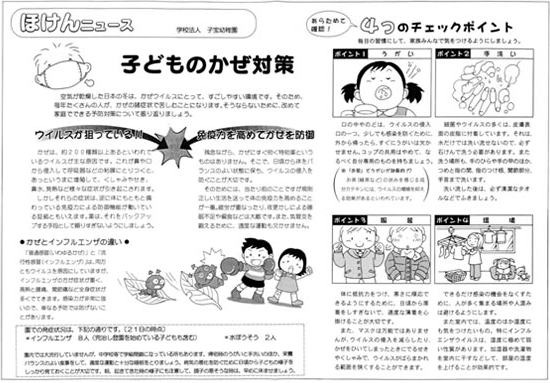
親子登園
毎月一回土曜日、9:00~12:00に園庭開放をしています。予約も費用もとらずに行っていて、在園児とその年齢に該当する子どもなら、他園に通っていてもかまいません。
そして、未就園児の子どもも参加します。安全な遊び場が少ない中で、皆さんに喜ばれていて、多い時には約200組の親子が参加してくれます。
園庭での遊びに加えて、保育室でのコーナー遊びも充実させています。
外部の方にお願いして、親子のふれあい体操や歌のお兄さんによるコンサートも行っていて、お父さんやお母さんも一緒に楽しい時間を過ごします。


「保護者と幼児の活動の機会を設けること」が重要視されている中で、園庭開放に力を入れています。
そして、子どもの活動にあったお店屋さんごっこの商品の1つを夏休みの宿題として、親子で製作してもらっています。
「めんどくさいなぁ」と感じている保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、一緒に何かをする「きっかけ作り」も大切にしたいと考えています。





その他にも、3. 保護者同士の交流と4.子育て相談にも力を入れています。
これらの活動が『親育ち』の一助になれば嬉しいことです。
近年、『子育て支援』ということが、盛んに叫ばれています。
母親の社会参画の為には、子どもを預かる施設も必要かもしれませんが、本園では子どもと親を引き離すことよりも親が自信を持って子どもと向き合える為の支援を模索していきたいと考えています。
保護者と保育者が理解し合い、協力する体制があってこそ、子どもの健やかな成長につながるのだと確信しています。
その為には、保育者側のコミュニケーション能力の向上も欠かせません。
専門家による園内研修を実施して、保育者のスキルアップに努めることと保育者が心身ともに元気に子ども達と接していける様、職員のメンタルケアにも留意しています。
保育内容の充実を含め、幼児期の教育のセンターとしての役割を果たせる様、まだまだ課題はありますが、一つ一つ克服していきます。

本園では、『人と共存していく力(コミュニケーション能力)を養う』というテーマで研究いたしました。
これには、3つの面があります。1つは子どもへの教育、もう1つは保護者への働きかけ、そして、保育者のスキルアップです。